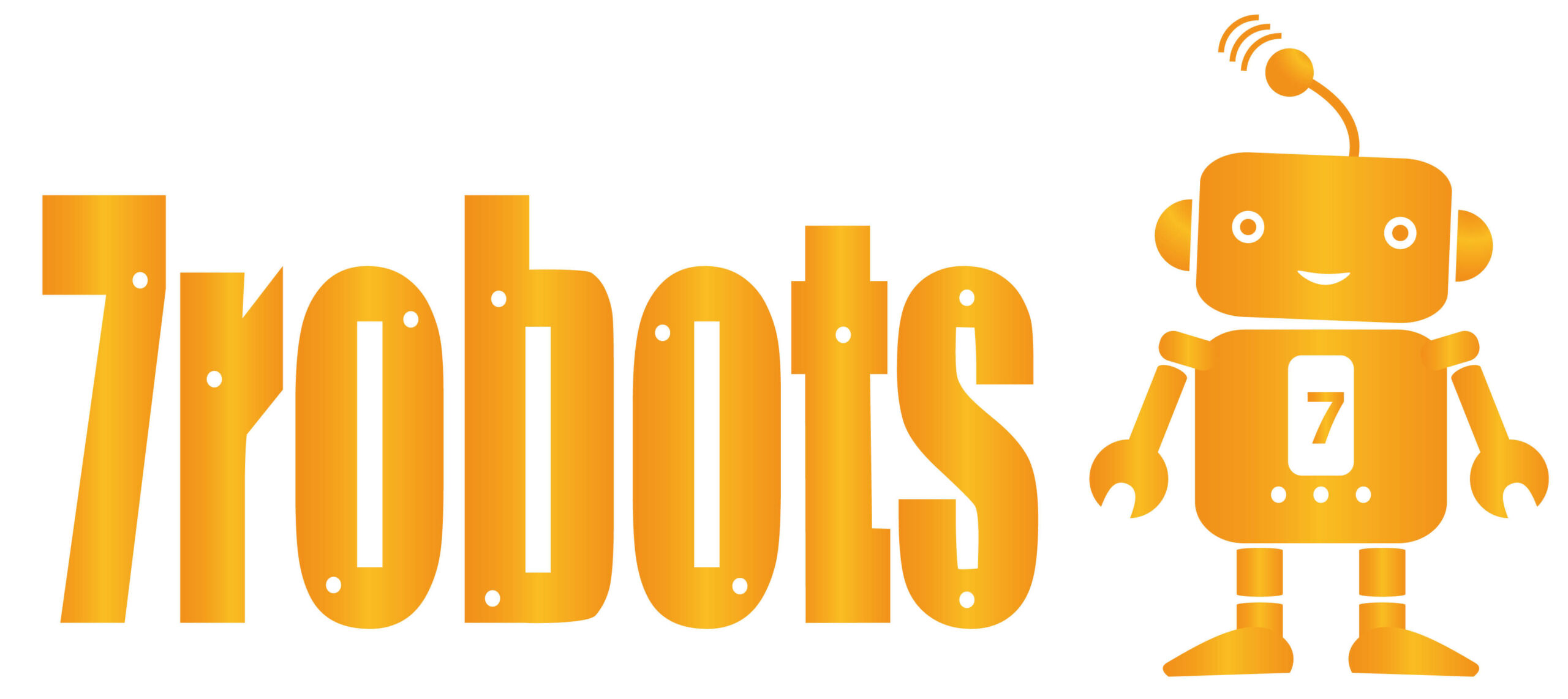「そのRPA内製化レッスンを選択すれば、PowerAutomateDesktopが使えるようになりますか?」
時折、受ける質問です。
高額なサービスですから、心配されるのは当然です。
結論を申し上げる前に、ちょっと説明させてください。
■RPAは「プログラミングもどき」である
RPAツールのメーカーは、「プログラミングの知識が無くても使える簡単なツールです。」と謳っています。
しかしその実は、「プログラミングの基礎知識があることを前提にツールは作られている」と言えます。
もちろん、そんなに高度な知識は必要ありませんが、ツールの裏側では何らかのプログラミング言語が動いている都合上、変数とかループとか、条件分岐といったものは必須になってきます。
この点に関しては、エクセルマクロを嗜んでいる人はすんなり理解できるでしょうし、全くのノンプログラマーの人には、その概念が腹落ちするまで時間が掛かるのは仕方がないのです。
そういえば、私も簿記三級を初めて勉強した時、なかなか「借方・貸方」の概念が腹落ちせず、理解するまでに時間が掛かりました。
でも、例題を複数解いていくうちに、誰でも理解できるようになっています。
RPAツールに関しても、個人差がある「そんなもの」と思って頂いて構いません。
■講義の仕方について
市販されているRPAツールの教材をみると、どれもほぼプログラミング教材と同じ教え方ですね。
つまり、
1.これからその章で学ぶことを簡単に説明
2.さあ、例題を手を動かしながら、一緒に作りましょう
3.補足説明
といった流れです。
プログラマーに「プログラミング習得のコツ」を聞けば、10人中10人がこう言います。
「実際に手を動かしてみること」
「1つでも多く、質の良い例題を解くこと」
これは、RPAツールを勉強する場合も同じ。
動画や書籍を眺めているだけでは、決して身に付かないのです。
最初は、書籍や動画の言われるがままに手を動かしていく形になりますが、それいいのです。
あと1つ付け加えるならば、RPAの内製化レッスンが終わった後、「自動化したい社内の作業を事前に見つけておくこと」です。
目標があると、自然と講義に対する集中力も上がりますからね!
■受講時の注意点
ただし、「今、自分は何をしている(何の機能を学んでいる)のか?を常に意識する」ことがとても大事です。
それ無しに手を動かしても、効果半減です。
そして、もう1つ私は付け加えたいです。
その小問(例題作成)が終わった直後、次の小問に進む前に、再度その例題の「肝は何だったのか?」を整理する(言葉にしてみる)ことです。
例えば、エクセルの処理が例題だった場合、
「RPAツールを使ってエクセルにあるすべての行を順番に処理させるためには、最終行をどうやって識別するのか?ということが大事である。その手法は・・・」
といった具合です。
こうして、なんとなく進めていくのではなく、1つずつ形にしていくことが大事です。
■受講後の注意点
私の経験上、数日のレッスンを終えて、その時点では分かったつもりになっても、3カ月ほどRPAツールに一切触れない生活をすれば、綺麗さっぱり忘れます(苦笑)
「鉄は熱いうちに打て!」と言われますが、その通りです。
あまり考えなくても、ある程度手が勝手に動くレベルまで、継続して形にすべきです。
最低限、「RPAによるエクセルブック編集(自動化)なら、教材を見なくてもできますよ!」というレベルまでは持って行っていただきたいと考えています。
また、レッスンの翌日には、さらりとでも良いので、「昨日、何を学んだのでしたっけ!?」と復習し、問いを見ただけで、フロー作成の手順が思い出せるレベルにして頂きたいと思います。
■結論
当方の教材で基本的な操作は、ほぼ網羅しています。
しかし、それでも完全ではありません。
自動化対象のアプリとRPAツールとの相性が悪く、該当しそうなアクションをそのまま使ったのでは、動かないということも結構あるからです。
最終的には、RPAも一般的なプログラミング同様、パズルの要素があり、「これがダメなら、あれを試してみよう」といった具合に試行錯誤する場面が必ず出てきます。
そういった「自走力」は、どうしても必要になります。
自分なりに「アウトプット」を繰り返していくなかで、RPAツールの癖や自動化パターンを覚え、初級者から中級者、中級者から上級者へと上がっていくのです。
繰り返しになりますが、当方の内製化レッスンにおいて、
・手を動かして、講義の例題を自分でも作ってみること
・何を今自分は行っているのか?を常に意識すること
・適度な復習とアウトプット
が伴えば、PowerAutomateを習得できると断言します。