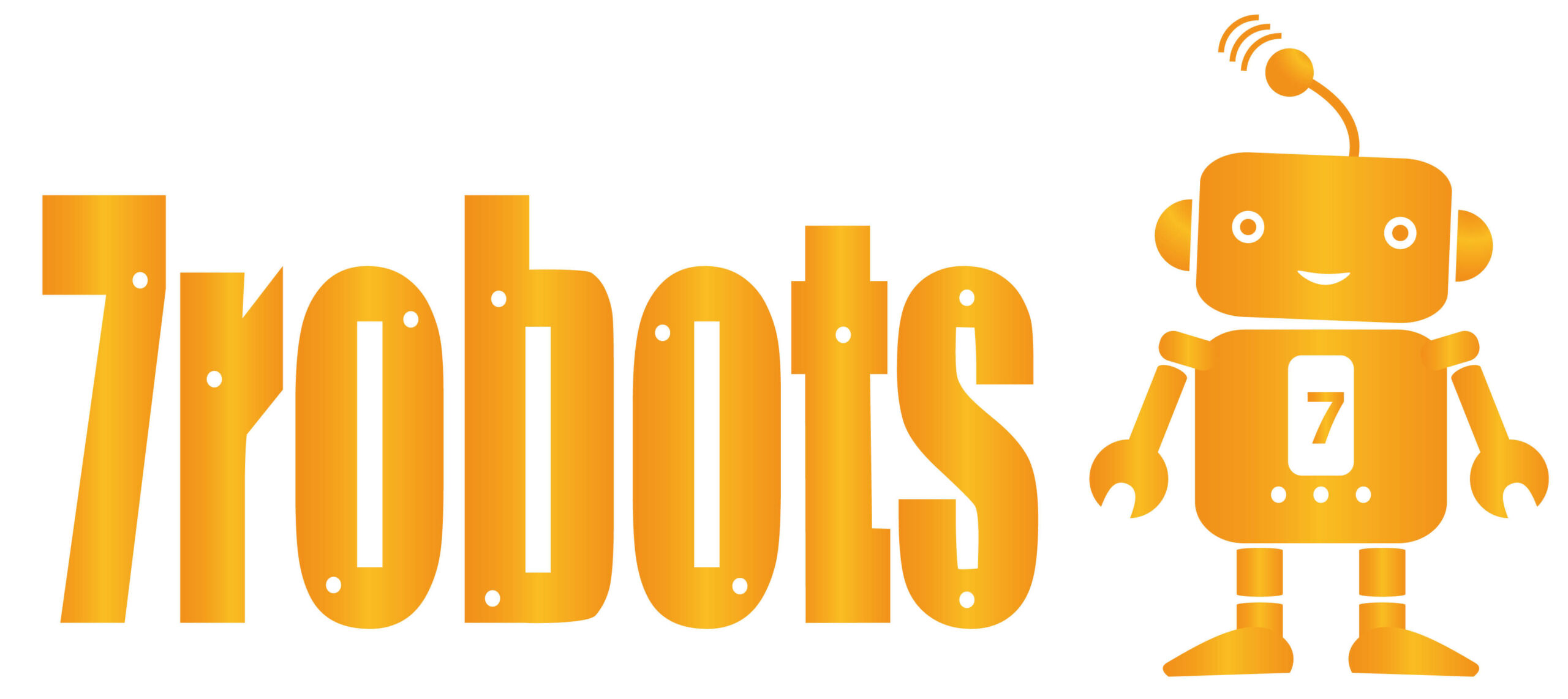ChatGPT3.5がリリースされたのが、「2022年11月30日」です。
まもなく3年というところですね。
あれから、世界は空前絶後の「AIブーム」になっています。
そして多くの評論家が、「AIが仕事を奪うぞ!AIに使われる側から、使う側に回れ!」と声高に叫んでいます。
AIがかなりヤバイ代物であるというのは、多くの人が感じていると思います。
その反面、自分事となった場合、「具体的に、何をすれば、AIを使っている側に回れるのか?」が分かっている人は少数だと思うのです。
今回、そこを掘り下げていきましょう。
■専門家の言っている「AI」とは何か?
AIという単語は、ご存知の通り、人工知能(Artificial Intelligence)のことです。
なのですが、あまりに幅広すぎて、ちょっとピンときません。
では、専門家の言っている「AI」とは何を指しているのでしょうか?
大半のケースで「生成AI」を指しています。
つまり、ChatGPTやGemini、CopilotといったLLM(大規模言語モデル)のことですね。
これを使いこなせるようになりましょう!と言っているのです。
■生成AIを使いこなすとは?
「生成AIを使いこなす」というのは、単に便利なツールとして使うだけでなく、あなたの創造性や思考を拡張するパートナーとして、主体的に活用することを意味しているのだそうです。
この生成AIは自然言語(話言葉)を解釈してくれるのが最大の特徴です。
そのため、プログラミングやITに詳しくない人でも、すぐにチャット形式で「それとなく」使えるのです。
しかし、その一方では、奥が深いツールであるとも言えます。
それは、「Gabage In, Gabage Out(ゴミを入れれば、ゴミが出る)」と言われるように、質問の仕方によって、出てくる回答が大きく異なるからです。
これは人間の会話をイメージして貰えば、分かると思います。
曖昧な質問をされれば、こちらも曖昧な答えを返さざるを得ませんよね?
生成AIを使う際のこの質問文を「プロンプト」と言いますが、このプロンプト作成スキル(質問力)というのが、重要になってくるのです。
■これからの企業の方向性
今、市販されている「プロンプト」についての本は多数ありますが、基本的に「プロンプト集」と言えるものばかりです。
つまり、「こういった雛型を使えば、より効率的にあなたが望む答えを貰えますよ!」という雛型集です。
また、社内で特定の雛型集を作成し、それをみんなで使い回すという企業も増えています。
それにより、メール作成時間などを削減できるという訳です。
その一方で、このLLMをベースとした、AIアプリケーションも多く出ています。
それらのアプリケーションを使うことで、わざわざプロンプトを考えなくても済むのです。(アプリ作成側が、事前に適切なプロンプトを設定してくれているため)
マネジメント層としては、社員にプロンプト集を強いるよりは、もうアプリとして提供した方がお金はかかるが、話は早く、品質もある程度均一化できるというメリットがあります。
■一般ビジネスマンがAIを使う側に回るために
では、会社からそういった指示がない場合には、どのようにスキルアップすれば良いのか?
世の中に「AI」を謳うツールが多すぎて、何から手を付けたら良いのか分からない!という人は多いと思います。
私の答えはこうです。
『今のスキルに関連するツールから手を付けろ!』
流行りを追っかけて闇雲にツールを一通り学習しても、実際の仕事で使う機会がないものは、すぐに使い方を忘れてしまいます。
そうではなく、あなたの日常業務の中で「これを簡略化・自動化するAIツールは無いか?」という観点からアプローチするのが良いでしょう。
ピンとくるものが無ければ、一番アレンジの効きやすい、生成AIから始めるのが良いのかもしれません。
最初は文書作成から入り、画像生成の必要が出てきて、そのうち動画作成の必要も出るかもしれません。
そうやって枝を伸ばしていくことで、生成AIの癖なども理解できるので、もし新しい分野のAIツールを学習する必要性が出た時にも、敷居はかなり低くなっているはずです。
あとは、RPAなどのローコード・ノーコードツールも良い選択肢になると思っています。
なぜなら、最近のローコード・ノーコードツールにも、AIが組み込まれ始めているからです。
私が以前のブログで予想した通り、「将来、RPAはAIに取り込まれてしまい、誰も”RPA”なんて単語を使わなくなる」という未来に近づいている気がします。
ですので、生成AIマスターになるのも良いですが、将来性のあるローコード・ノーコードツールの勉強も同じくらい有望だと思うのです。
まあ、どれか1つを選ばなくてはいけない訳ではないし、生成AIなんて、作成者側ですら「何をどこまで出来るのか分かっていない」サービスです。
まだ黎明期と言える時期ですので、いろいろ触って覚えるくらいの感覚で最初の一歩を踏み出すのが良いと思いますね。