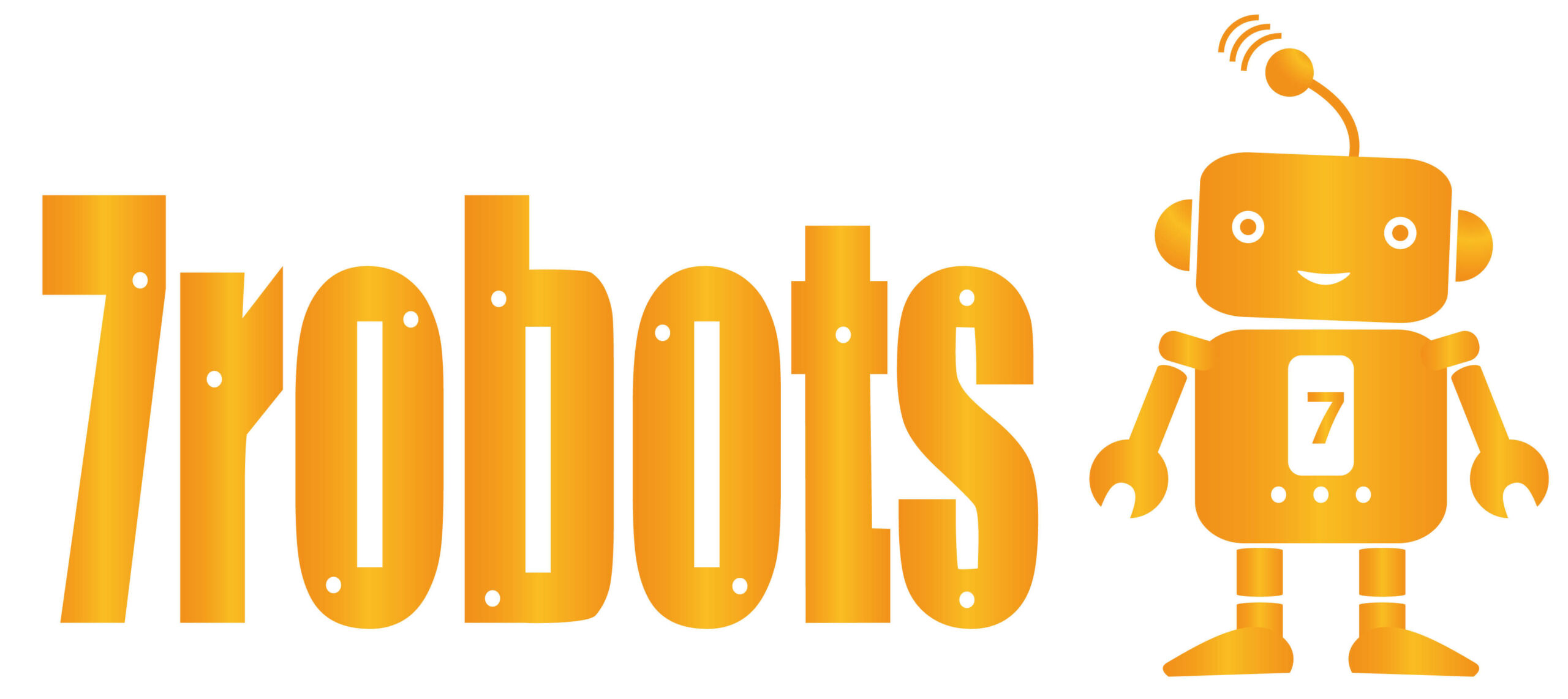以前書いた記事、「北見市の財政再建」へのアクセスが思っていた以上に多いことに驚きました。
検索エンジンでも上位に表示されているからでしょうか。
それとも、北海道だけの話ではなく、全国で「他人事ではない」と考えている自治体が多いからでしょうか。
また、北海道の有力メディアである「北海道新聞」が堂々と「有識者が北見市は間違いなく財政破綻すると警鐘を鳴らしています!」と報道し始めています。
通常は市民への配慮からそういった断言はしないはずですが、よほどその事実に自信と証拠があるのでしょう。
そこで、再度AIの力を借りて、「夕張で起こったことをベースにして、もし北見市が財政再生団体入りしたら、実際にどのようなことになるのか?」を描いてもらいました。
文章を読んでみて、ゾッとする内容ですが、財政破綻は行政サービスだけでなく、地域の経済全体、そして生活そのものを崩壊させることを理解しなければなりません。
なお私は、今、正しい対策を打てば、ギリギリ間に合うと考えています。(今、現在進行中の財政再建策は間違っていると考えます)
—
🥶 北見市を待ち受ける「財政再生団体」のリアルと極寒の冬
北見市がもし「財政再生団体」に移行した場合、それは借金返済のために国から行政運営を管理される、事実上の地方自治体の破産状態です。
特に北海道の豪雪地帯において、その現実は想像を絶する厳しさとなります。
—
👨👩👧👦 市民を襲う「サービスの崩壊」と生活コストの高騰
財政再生団体になると、市民が長年享受してきた公共サービスは容赦なく廃止・縮小され、同時に負担が大幅に増加します。
1. 料金の超高騰と負担増
サービスの削減と同時に、行政が提供する公共サービスやインフラの利用料は、財源確保のために大幅に値上げされます。
水道、下水道、市立病院の診療費などが、民間の相場やそれ以上に引き上げられます。
2. 「大きなハコもの」の廃墟化と撤去
「平成の大合併」の負の遺産として建設された新庁舎、体育館、交流施設などは、維持費が捻出できず、容赦なく閉鎖・売却・撤去の対象となります。
* 図書館・博物館: 分室・分館は閉鎖され、開館時間やサービスも大幅に縮小。過去の投資の象徴であった施設が廃墟化し、市民の誇りやアイデンティティが傷つけられます。
* インフラの放置: 道路、橋、上下水道などの老朽化対策が後回しになり、市民の安全を脅かすレベルまでインフラの劣化が進みます。
3. 商業施設の連鎖的な撤退と経済の空洞化
行政サービスの低下と並行して、地域経済が深刻な打撃を受けます。
* インフラコストの重圧: 水道代や電気・ガス代などの公共料金が高騰すれば、特にエネルギーコストが高い北海道において、大規模商業施設や飲食店チェーンの固定費を強く圧迫します。
* 顧客の購買力低下: サービスの縮小と公共料金の値上げにより、市民の可処分所得が減少し、消費が冷え込みます。
* 市場の魅力喪失: コスト上昇と売上減少のダブルパンチにより、「この地域での事業継続は不可能」と判断され、多くのチェーン店や商業施設が撤退。生活の利便性が大幅に低下し、街全体が空洞化します。
4. 極寒の冬と公共施設の閉鎖
最も深刻なのは、北海道の市民生活に不可欠な暖房を含むインフラコストの削減です。
* 公共交通の消滅: 市営バスなどの公共交通機関は採算が取れないとして廃止・大幅に減便され、特に高齢者の「冬場の移動」が困難になります。
* 子育て環境の悪化: 保育所・幼稚園の統廃合、児童手当や医療費助成の縮小により、子育て世帯にとっての住みやすさが大幅に低下し、若年層・ファミリー層の流出が加速します。
—
👤 職員を襲う「大規模リストラと極限の勤務環境」
市役所職員は、財政再生の最大の実行部隊であり、最も厳しい立場に立たされます。
1. 大規模な人件費削減とリストラ(職員数の半減)
財政再生団体になると、国から再生計画の策定を命じられ、その柱の一つが人件費削減です。夕張市の事例では、職員数を合併前の約半分まで削減しました。
* 早期退職・解雇: 希望退職の募集、さらには解雇(分限免職)も行われ、長年市民のために尽くしてきた職員が職を失います。
* 給与の大幅カット: 市長以下の幹部職員の給与は最大30%カットされ、一般職員の給与やボーナス、各種手当も、国が定める基準まで引き下げられます。
2. 真冬の暖房停止と士気の崩壊
最もリアルで象徴的な削減策が、エネルギーコストの徹底的な抑制です。
* 行政機能の麻痺: 夕張市の事例では、コスト削減のため、市の施設や出先機関で真冬にもかかわらず暖房が止められ、職員はコートを着込んで仕事をせざるを得ませんでした。北見市でも、暖房費、電気代の削減は再生計画の重要なターゲットとなり、極寒の環境下での勤務が常態化する可能性があります。
* 業務量の激増と苦情対応: 職員の数が半減する一方で、市民サービスの低下に対する市民からの怒りや苦情の矢面に立つことになり、精神的な疲弊は極限に達します。
—
👔 市議会・市長を襲う「権限の喪失と報酬の減額」
財政再生団体への移行は、市民から選ばれた政治家や首長の権限の事実上の停止を意味します。
1. 市長の権限の喪失
* 予算編成権の喪失: 市長が作成した予算案は、国が任命した専門家や監督機関によって厳しくチェックされ、事実上、国が示した再生計画の通りにしか予算を組めなくなります。市長は「調整役」となり、自らの政策を実現する権限はほとんどなくなります。
* 対外的な信用失墜: 市長が経済団体や企業に誘致や協力を呼びかけても、「破産した自治体」というレッテルにより、誰も耳を貸さなくなります。
2. 市議会議員の報酬の大幅減額と活動の制約
市議会議員もまた、財政再生計画の対象となります。
* 報酬の大幅カット: 議員報酬は、行政改革の一環として大幅に減額されることが不可避です。夕張市では、財政破綻後に議員定数の削減(18人⇒9人)が行われるとともに、議員報酬も大幅にカット(月額約31万円⇒約16万円へ)されました。北見市でも、議員としての地位に見合う報酬が維持できなくなり、議員のなり手がいなくなる事態も想定されます。
* 審議権の有名無実化: 市議会は予算や条例を議決する権限を持ちますが、財政再生計画に基づいた予算案は、国の同意を得たものであり、市議会が反対しても通らざるを得ない状況になります。議員は、市民からは「市の財政を破綻させた責任者」として厳しく糾弾され、市民の怒りを代弁する以外の役割を果たせなくなります。
3. 再生期間の長期化
財政再生団体に移行した場合、再生計画期間は10年、15年、あるいはそれ以上に及びます。北見市が夕張市のような地方自治体史の「負の教訓」として、長期にわたって自由な行政運営を奪われることになります。
—
🛑 結論:削減策の限界と「攻め」への転換が唯一の道
北見市が財政再生団体に移行した場合、それは「借金を返すための行政」に変貌することを意味します。
極限のコスト削減は、市の誇りや活力を根こそぎ奪い、商業施設の撤退も相まって、「道東の中心都市」としての地位を完全に失墜させます。
⚠️ 現在の削減策は「歳入の前借」に過ぎない
現在、北見市で進行中の財政再建策のほとんどは、サービスの縮小や施設の売却といった「削減」です。
中には、子育て支援やインフラの維持管理といった、将来の世代への投資として削ってはいけない項目も多数見られます。
これは、将来の財産やサービスを売って、今すぐ必要な歳入を一時的に補う「歳入の前借」に過ぎず、恒常的な財政健全化には繋がりません。
✨ 唯一の道筋は「外部の力を借りた攻めの財源確保」
再生団体入りを回避するには、市民、職員、市議、そして市長が、この「リアルな地獄」を共通認識として持ち、従来の政治や行政の枠を超えた抜本的な改革が不可欠です。
それは、外部の知恵と実行力を借りて「攻めの財源確保」へと舵を切ることです。
もちろん、今行っている財政再建案を作った時にもそれなりに外部の専門家にアドバイスなどを求めたと思いますが、その規模や質では、全然足りないのです。
改革の主導権を最適な人材に委ねるというレベルでないと奏功しないでしょう。
専門家の導入: 外部専門家に裁量権を与え、しがらみなく資産の売却や行政組織の再編を断行する。
攻めの誘致: 税制優遇や特区制度を大胆に活用し、地域の特性を活かした高収益企業を誘致し、恒常的な法人税収と雇用を確保する。
「お金」を生み出す構造を根本から変革し、未来への投資を止めないこと。それが、北見市に残された唯一の現実的な選択肢です。