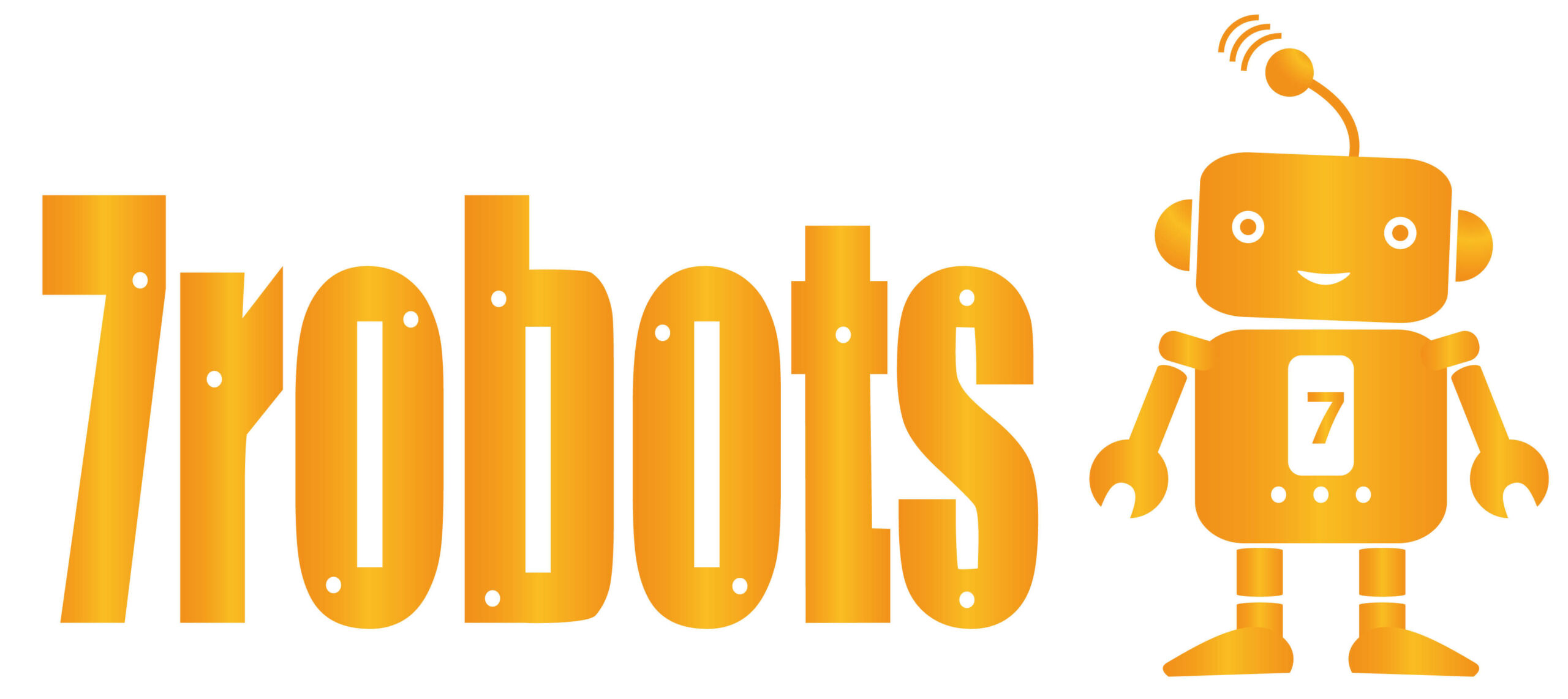1. この話題に辿り着いたきっかけ
私は日常的に、ChatGPTと様々なテーマについて議論を交わしています。弊社ではChatGPTの活用を支援するレッスン教材も扱っており、対話を通じて構想を整理したり、新しい発見を得たりすることが少なくありません。
ある日、ふとこんな問いをChatGPTに投げかけました。
>「町おこしって、もう限界の町もあるんじゃないですか?」
AIは当然のように、町おこしの成功事例を列挙してきました。移住促進、観光資源の再発掘、地場産業のブランド化、地元住民の情熱…いわゆる「希望の物語」が並びました。ですが、私はどこか引っかかりを感じました。
>「でも、誰がやっても無理な町って、現実にありますよね」
この素朴な違和感が、私の考えを大きく変えていきました。AIとのやり取りを重ねる中で、次第にこう思うようになったのです。
町おこしではなく、「町の終活」という考え方が必要な時代が来ているのではないか。
これは暗い話に聞こえるかもしれませんが、むしろ私は、誇りある終わり方を選ぶことこそが、町と住民の尊厳を守る道ではないか?と考え始めたのです。
2. 街の成り立ち——「そこにある意味」があった時代
かつての町には、「そこに人が集まる地政学的な理由」が必ずありました。水の流れ、峠越え、街道の分岐、漁場、鉱山、藩政の拠点──すべての町には「その場所でなければならなかった」理由があったのです。
私の故郷である岡山県の北部にある町もそのひとつです。中国山地に囲まれた盆地にあり、山陽と山陰を結ぶ中継地として、それなりの役割を果たしていました。林業や農業も活発で、人々の暮らしがそこに根付いていたのです。
しかし、現代のテクノロジーやインフラ整備が進んだ結果、「その場所でなければならない」という根拠が徐々に失われつつあります。
今までも大半は「村」レベルですが、その存在根拠を失い、時代の流れの中で「記録」として消えていったというのは珍しくありませんでした。
3. 交通網の発達と「町の意味」の喪失
現在、日本の交通網は高度に発達しています。高速道路を使えば県をまたぐ移動も簡単で、LCCを使えば1万円以下で日本中どこへでも行けます。物流は大動脈を使った集約型になり、小さな町に中継地としての役割を求める必要はなくなりました。
加えて今後は、自動運転技術、ドローン配送、遠隔診療、キャッシュレス社会などの普及によって、人をその地に縛り付けるものが、どんどん無くなってくる時代に入ります。
「昔はここが拠点だった」と言われた場所に、もう人も役割もない。
それでも町を残そうとする努力は尊いものですが、果たして、それは持続可能なのでしょうか?
仮に町からとんでもなく出世した人が出て、故郷へのお返しとして100億円寄付したとしても、それは一過性の盛り上がりになる可能性が高いでしょう。何かキラーコンテンツになるようなものが元々存在しない土地で、ゼロからあれこれアイデアを出して、それを元に今から町再生の道筋を作っていくというのは、あまり現実的ではないと思っています。
4. 国は「全体最適化」を優先せざるを得ない
ここで、より大きな視点──国家レベルの視野に立って考えてみましょう。
これからの日本は、急速に人口減少と高齢化が進み、自治体の数を維持するにも、道路や水道といったインフラを維持するにも、膨大なコストがかかるようになります。財源は限られており、あらゆる公共サービスを全国に等しく届けるのは物理的にも財政的にも不可能になります。
そこで国家はやむを得ず、「選択と集中」による全体最適化へ舵を切るでしょう。つまり、拠点都市や特定地域に人口と機能を集約し、効率的な行政・医療・教育・交通を提供する仕組みに移行していくことになります。
これは冷たい判断ではなく、”国家が持続するために不可欠な戦略”です。私たち市民も、「町を残すか、社会全体を保つか」というジレンマの中で、いつか決断を迫られる時が来るのです。
5. 「消滅可能性都市」とは何か
2014年、民間シンクタンク「日本創成会議」は、「消滅可能性都市」という概念を発表しました。
その定義は以下のようなものです:
> 2010年から2040年までの30年間で、20〜39歳の若年女性人口が半分以下に減少する自治体
この“若年女性の減少”という指標は非常に重要です。なぜなら、出産・子育ての主体となる世代が減れば、当然その町の将来人口は激減し、やがて自然消滅に近い形で町そのものが存続できなくなるからです。
この指標によって、全国の896自治体が「消滅可能性都市」に分類されました。
私の地元もその一角に含まれています。
重要なのは、これは“将来の話”ではなく、“すでに始まっている過程”だということです。
6. 「町の終活」という視点を持つ時代へ
ここで、私が提案したいのが「町の終活」という視点です。
終活とは本来、人間が自分の人生の終わり方を考え、遺される人たちに迷惑をかけないよう準備する行動を指します。これと同じことを、「町」にも適用して考えるべきだと思うのです。
無理な延命ではなく、静かに、美しく、誇りある幕引きを設計する。
たとえば──
– 小中学校の統廃合と拠点化
– 集落の集約と公共サービスの集中
– 空き家の計画的解体と緑地化
– 歴史や記録のアーカイブ化
– 町の記憶を伝える小規模な記念施設
このようなプロセスを通して、町が「記憶」として生き続ける道を模索するのです。
7. 町が消えても、記憶は残る
今後、10年、20年の間に、全国の自治体が「残すか、閉じるか」の判断を迫られるようになります。
「平成の大合併」がおこなわれたのは、「1999年〜2006年くらいの間」です。ついこの前のような気がしますが、すぐに第二次合併、第三次合併が必要になってくるでしょう。
そのとき、市長や知事が市民に説明する材料として、この“町の終活”という概念が必要とされる日が来ると確信しています。
もしかしたらその頃、ある学者がこの概念を本にまとめ、テレビで解説し、各地の政策に反映されているかもしれません。
私はそれでいいと思っています。大切なのは、「誰が言ったかではなく、何が伝わったか」だからです。
町おこしがすべて悪いわけではありません。でも、もう限界に来ている町もある。その現実から目をそらさず、静かに、でも前向きに町の“人生の終わり”を考えていく。そんな時代に、私たちはもう足を踏み入れているのではないでしょうか。